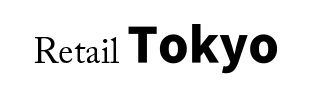動画が「販促の一手段」だった時代は終わりつつあります。SNSでの共感消費、来店前の情報収集、インフルエンサーとの接点設計など、小売業界における動画の役割は劇的に広がりを見せています。
では、小売業界はこの変化にどう向き合うべきなのか? そして、現場では何が起きていて、何を整備すべきなのでしょうか?
今回は、Fireworkリテール事業責任者の松本 一穂(以下:松本)が、オムニチャネルの専門家でありFireworkアドバイザーでもある逸見光次郎氏(以下:逸見)を迎え、動画の「使い方」が顧客体験と購買行動にどのように作用していくのかを深掘りします。
小売における動画活用が注目される背景
販促ツールから顧客体験設計ツールへ
松本:
本日はお忙しい中お時間をいただきまして誠にありがとうございます。
まずは今とても注目されている動画の活用について伺っていきたいと思います。小売における動画は従来の“一方的に商品プロモーションを行うための動画”という位置づけから明らかに変化していると思います。たとえば実店舗での接客を補完するような形で、動画が顧客との信頼関係構築に寄与していたりします。
逸見さんからみて、動画の活用方法が変化していることについてどう思われますか?
逸見:
はい。今は「売るため」ではなく「選ばれるため」に動画を使う時代。小売における動画は、接客や体験の再現に近いツールとしての可能性を持っています。 Fireworkのような動画マーケティング ソリューションはもちろんですが、撮影機器の進化も目まぐるしいので、この分野はまだまだ変わっていくと思います。本当に時代の進化に追いつくだけでも大変です。

コロナ以降、情報と購買が分断され、動画は“接客”と“安心”を届ける存在に
松本:
そうですよね。IoTやAIなど、本当に進化が激しいですよね、紙からWebへ、そして動画へと時代が移り変わっていくのでしょうね。
さて、次に消費者やマーケットのトレンドについて教えてください。コロナ禍を境に消費者の購買行動が大きく変化したように思うのですが、いかがでしょう?
逸見:
購買行動は大きく変わりましたね。コロナ禍以前から「オムニチャネル」や「OMO」などは概念はありましたが、コロナ禍で店舗に行けなくなって、人々がオンライン上でコミュニケーションしたり、ネットで買い物することが一気に日常となりましたね。
そして、面白いのがコロナ禍以降ではオンラインで情報を集め、実店舗で購入するという流れが加速しました。店舗回帰といいますか、実店舗で買い物できなかった反動もあるかもしれませんが、コロナ禍で店舗にいけなかったからこそ、ECサイトにはない店舗の良さが見直されたのだと思います。
この流れによって、小売にとって「情報の質と量」がより重要になっています。
松本:
なるほど。「情報の質と量」が重要になってくると。情報の量については、考えるまでもなく、SNSをはじめ大量の情報が溢れていますし、爆発的に増加しているのは各種データはもちろん、体感値としても理解できます。
情報の質についてですが、正確さという意味でいくと、商品スペックであれば検索すればいくらでもネットで情報は得られます。場合によっては、店舗スタッフに聞くよりもネット検索した方が正確で質の高い情報が得られるかもしれません。一方で商品の使い方や、肌触りや重さなどのリアルな情報が求められていると思うのですが、いかがでしょうか?
逸見:
まさに、その通りです。リアルな情報を届けることこそ、動画の役割だと思っています。店舗でしか得られないようなリアルな情報を「接客の疑似体験」として、動画で伝えることで顧客の不安を和らげてくれるわけです。
ライブコマースの可能性と、小売現場の活用
店舗スタッフの“接客力”をオンラインに載せる
松本:
店舗ではなく、オンラインで接客する手段としてライブコマースがあります。まさにリアルな情報、つまり質の高い情報を届けるためにライブコマースが注目されていますが、小売企業がライブコマースを成功させる秘訣はどこにあるとお考えですか?
逸見:
ライブコマースを成功させる鍵は、「誰が伝えるか」が重要です。接客のプロである販売員がライブで紹介することで、顧客の信頼を得やすくなります。これは、オンラインでもリアルな体験を求める今の消費者心理にしっかりフィットしています。
松本:
1対1の接客では得られない、「他の人の疑問」もライブ配信ではカバーできますね。誰かがチャットでした質問に対して回答することで、視聴者の理解も深まりますし、まさに“共有型接客”としての価値が高いです。
逸見:
気になっていたけど聞けなかったことを誰かがチャットで聞いてくれると嬉しいですよね。また、商品の感想もチャットで見ることができるので、自分以外の方々の情報って本当に安心できますよね。
CM品質ではなく“伝わる動画”を目指す
松本:
多くの企業様からライブコマースも含め、動画を制作すること自体に対するハードル・障壁・悩みがあるように感じます。確かに、一般的に動画は写真に比べて工数もかかりますし、クオリティを担保するにはノウハウも必要だと思われているようです。二の足を踏んでしまう気持ちは理解できるのですが、この点はいかがですか?
逸見:
そうですよね。動画というと、ハードルが高いと思ってしまう方も多いと思いますが、正直iPhoneで撮った動画で十分です。むしろ“等身大の目線”が、顧客からの信頼感を得やすいですし、豪華な演出よりも「リアル」が刺さる時代です。
松本:
なるほど。等身大の動画であれば、簡単に動画を撮影できますよね。一方で、手軽に撮影できてしまうことで「炎上」を心配する企業様も多いのですが、いかがでしょう?
逸見:
動画はSNSではないので、ルールとチェック体制を整えれば安全でしょう。普段の接客が成立しているなら動画も問題ありません。販売員の現場力を活かすことが、むしろブランドの信頼につながります。
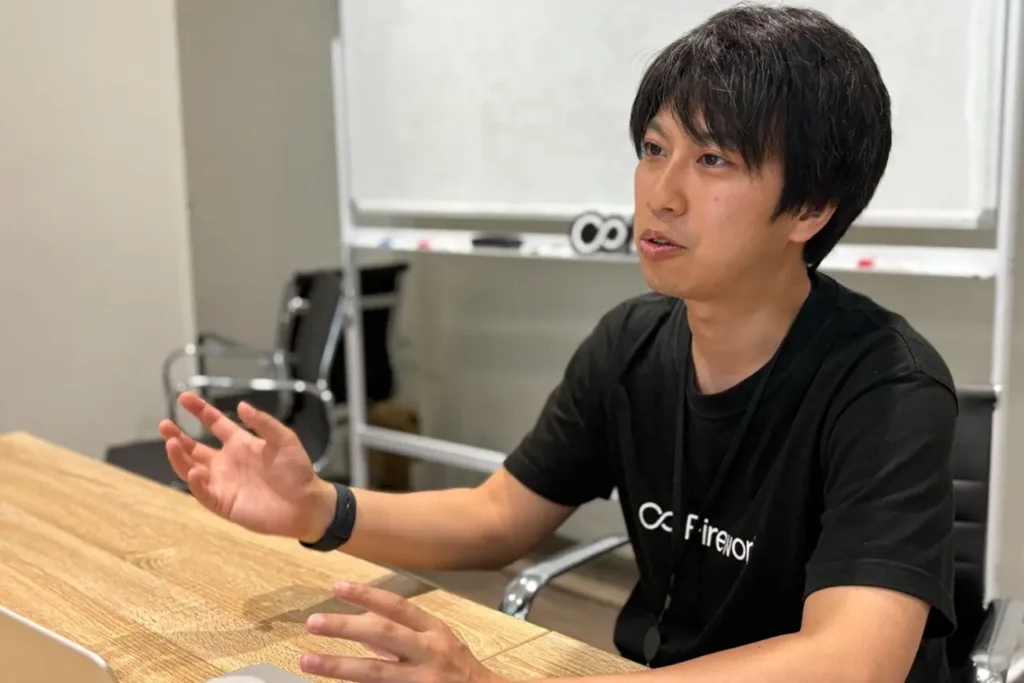
動画活用の成功事例とこれからの展望
松本:
今後は、顧客ごとに最適な動画を届ける“パーソナライズ動画”が主流になる可能性もありますね。AIを活用した“動画接客”の時代がすぐそこまで来ていると感じますね。
逸見:
2026年は“動画コマース元年”として、企業が「動画の使い方」を磨くフェーズに入るでしょう。動画はもう「特別なコンテンツ」ではなく、「顧客との会話の手段」になりつつあります。
松本:
販促ではなく、接客と信頼づくりのための動画活用。それが、小売業界が変わる鍵になると感じました。動画を“活用する力”こそ、これからのリテールDXにおける差別化の軸になるはずですね。
本日はお忙しい中ありがとうございました!